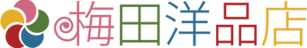お針子だより
2024年ジャワ島(アフリカンプリント布の源流)への旅【後編】
前編では、「なぜジャワ島を訪れたのか」を記しました。 今回は後編というか本編です。「ジャワ島で何をしてきたのか」という内容です。 写真中心ですので、さくっとお楽しみくださいね。 まずはジャカルタから。ヒジャブについて。 ジャカルタ到着翌日には、数年前に日本で知り合ったインドネシア人の方と再会できました。現地のことをいろいろ教わり、心強かったです。 出会ったころの彼女はヒジャブ姿ではありませんでしたが、最近になって着用を始めたとのこと。 「多様性の中の統一」が国のスローガンで、「国教」は定められてません。ヒンドゥ教や仏教の影響も残ってます。でも人口2億7千万人の9割弱がムスリムとのこと。 そのうちのムスリム女性のヒジャブ着用率は、少なくとも6割以上のようです。 教育を受けた女性が増え、その社会的地位の上昇とともに、自主的なヒジャブ着用率も上がっていったと言われてます。現地ユニクロでもヒジャブを売ってました。 都市の若い世代ほど髪を隠すようになったというのは、不思議な気もします。親世代からの自立の証なのでしょうか。 国民的英雄チュ・ニャ・ムティア(反オランダ闘争の女性指導者)はたぶん(名前を冠したモスクもあるくらいなので)ムスリムですが、肖像では髪を隠してません。2024年12月現在1000ルピアは約9.5円です。 ちなみに、あるところでお会いした姉妹は、未婚の妹がヒジャブ着用で、結婚していて子もいる姉はというと、ヒジャブは着用せず、それどころか髪の一部をビリー・アイリッシュのように青色にカラーリングしてました。 ふつう、結婚姉と未婚妹でスタイル逆のはずでは…とつい思ってしまいましたが、偏見、思い込みですね。姉妹はお互いの信条を尊重してました。 ジャカルタに来たネルソン・マンデラ。晩年はバティック(を模した南ア製)のシャツの愛用者でした。 博物館にあの自由な生物が… ジャカルタの繊維博物館ではトゥバンというジャワ島の東北にある土地のバティックを特集してました。また、20世紀初頭の手描き作業によるバティックが多数展示されてました。 館内をツアーガイド志望の学生ボランティアさんが案内してくださいました。在籍してる職業学校のカリキュラムの一環だそうです。 猫が展示物の上に寝そべっていて、びっくり。 「お手を触れニャイでください(猫は足だからセーフ)」。 誰も追い出そうとしてなかったのがよかったです。いや、よいのでしょうか…。 ジャカルタでは、郊外のテーマパーク内にあるバティック博物館にも行きました。 ところで、これらの施設では英語案内が少なく、日本で発行されたクレジットカードは使えないなど、首都ジャカルタでさえ外国人旅行者にとっては、すこし不便でした。 逆に、それだけじゅうぶんな内需があるのでしょうね。なにしろ人口が世界4位の国です。 ジャカルタのガンビル駅は日本の駅を参考にしたようです。ここから次の都市ソロ(行政上の名はスラカルタ)へ、特別列車で7時間かけて行きました。 ソロ(別名スラカルタ) 内陸の古都ソロは、前大統領ジョコ・ウィドド(通称ジョコウィ)の出身地です。 インドネシア史上はじめての庶民派(非軍人、非政界エリート)の大統領でした。ちょうどかれの任期は私が滞在した10月まででした。2期10年、お疲れ様です。 そのソロには街中いたるところに伝統的バティックの意匠が。 右下のはジャカルタからの列車内でいただいたお弁当です(よく見るとスリーブにバティックの柄)。 ソロでもバティック博物館へ。...
2024年ジャワ島(アフリカンプリント布の源流)への旅【前編】
左が西アフリカのパーニュ、右がジャワ更紗 今年も梅田洋品店は10月にお休みをいただきました。 いつもはアフリカ大陸へ買いつけ旅をするための恒例のお休みですが、今回はある目的があってインドネシア(のジャワ島の3都市)を訪ねることにしました。 なぜジャワ島へ? 梅田洋品店が服作りに使っているのは「アフリカン・プリント」です。 細かく言うと、東アフリカの「カンガ」や南アフリカの「シュエシュエ」も使いますが、西アフリカの「パーニュ」がメインです。 左からコートジボワールのパーニュ屋さん、ケニアのカンガ屋さん、南アフリカのシュエシュエ屋さんにて。サイズやデザインの特徴がそれぞれの布で異なります。 「パーニュ(仏語で『腰布』)」は英語圏では「ワックスプリント」とも呼ばれます。つまり「ろうけつ染め」を模した機械プリントのことです。 「アフリカ布」という呼び方も最近は耳にしますが、多くの人がそれでイメージするのも、伝統的な布(泥染め布、ラフィア布等)ではなく、この西アフリカで多く売られているパーニュ=ろうけつ染めを模した機械プリントの布ですよね。 そう、「ろうけつ染めを模した」… ろうけつ染めといえば、ジャワ語で「バティック」…! じつは、「パーニュ」の源流はインドネシアのジャワ島にあるのです! 歴史をざっくりと… ちょうど梅田洋品店を始めた2006年に国立民族学博物館で更紗の特別展が開催され、大阪まで行ったことを覚えてます。 私の理解では、「西アフリカの機械プリントの布の歴史」はざっくり以下のようです。 ★15~17世紀の大航海時代に、インドのプリント布(インド更紗)が世界中に伝わる。日本にも。 ↓★ジャワ島でもインド更紗を参考にしたと思われる「ろうけつ染め(バティック)」が独自に発展。ただし王族用として。伝統的なバティックの特徴は、ロウを布の両面に置いて表裏まったく同じに染めること。柄のモチーフは波や剣、椰子の実、星、花など。「忍耐力」「愛と幸福」などの意味が込められていた。ジャワ人の多くが信仰しているイスラームの教えにより、人物や動物のモチーフはなかった(インドや中国の影響による神鳥や蛇神、孔雀の羽の柄などはあり)。 ↓★18世紀後半の産業革命期にイギリスでローラーを使う機械プリントが発明される。18世紀末にイギリスは機械織りの布を大量生産して、植民地インドに輸出。そのためインドの手織り布産業は衰退。 ↓★オランダは17世紀からインドネシアを支配。19世紀、オランダはローラーによるろうけつ染めを開発。「模倣バティック」を大量生産。ジャワ島に輸出…したのですが… ↓★インドの例とは異なり、ジャワ人は負けずに生産性を向上。手描きだけでなく、ブロックプリント(銅のスタンプ=チャップ)も使い、バティックの量産を可能にした。欧州からの大量の綿布の流入もあった。価格も求めやすくなり、大衆化(ただし、「王族以外は着用厳禁の柄」はあった)。 ↓★それに、オランダの模倣バティックは「ロウのひび割れ」が残っていた(現在でもそう。いかにも「ろうけつ染め」に見せるため、あえてそのように製造?)。ジャワ人の好みには合わなかった。 ↓ところが、同じくオランダ領だったゴールドコースト(現在のガーナ)に模倣バティックを輸出すると、デザインも質もたいへん好まれた(それ以前に、兵士としてジャワ島に派遣されていたアフリカ人たちが模倣バティックを持ち帰っており、そのときから人気だった――という説も)。 ↓アフリカ人の好みに合わせて、線を太く、色を明るくデザイン。モチーフには傘や扇風機等の道具のほか、人物含む生き物の絵も。 ↓以来、イギリスや中国の企業も製造と輸出を始めたり、現地にも工場ができたりして、「パーニュ(ワックス・プリント)」は西アフリカ各国の市場にあふれ、「アフリカ布」を代表するまでになった――。 まとめると以上のようです。主な参考資料は以下です。 国立民族学博物館『更紗今昔物語―ジャワから世界へ』 アンヌ・グロフィレー『ワックスプリント―世界を旅したアフリカ布の歴史と特色』 遠藤聡子さん(ブルキナファソとコートジボワールでお世話になりました!)『パーニュの文化誌-現代西アフリカ女性のファッションが語る独自性』 グロフィレーさんによれば、パーニュ(ワックスプリント)は「適応と模倣から生まれた不思議な布」。 実際、バティックの柄の名残もあります。 「西アフリカの機械プリント布の源流はジャワ島にある」という意味がおわかりいただけたでしょうか。 もっとも、今回ジャワでお会いしたバティック博物館のガイドさんも、バティック工房のスタッフさんも、西アフリカのパーニュとその歴史についてはご存知ないようでした。 「うちが元祖だよ」と、もっと自慢していいかもしれませんね。 続きは後編で… ともかくそういうわけで、この18年間はアフリカにばかり行ってましたが、「ジャワ島にもいつか!」とずっと思っていたのです。 ようやく、今回ジャワの3都市をまわることができました。...
2023年南アフリカ共和国への旅
7年ぶり6回目! コロナ禍の数年間はアフリカはもちろん、どの国にも行けませんでしたが、2023年10月にようやく買い付けの旅を再開することができました。今回の行き先は多くの友人知人がいる南アフリカ共和国にしました。 よく数えてみたら、2000年〜2002年にボランティアで滞在してた隣国ジンバブエからは3回、その後2008年と2016年にも南アを訪問しています。 というわけで、今回で通算6回目の南ア入国でした。じつは私が最も多く訪れてる外国かもしれません。 まずは大西洋に面したケープタウンに滞在し、それからインド洋に面したダーバンへと飛び、最後は最大の都市ヨハネスブルグに行くという計画を立てました。 この投稿をInstagramで見る 梅田洋品店(@umeda_yohinten)がシェアした投稿 ケープペンギンとの再会は… ケープタウンでは、ジンバブエ人の友人と再会することができました。世界遺産「カーステンボッシュ国立植物園」を案内してくださいました。 彼女とは2013年にジンバブエで出会い、2017年にはナイジェリアでもお世話になりました。今回でまさかの3カ国目での再会! ご覧の通り、10月上旬のケープタウンはまだ寒かったです。「この冬(7月~9月)は、ケープタウンに暮らした数十年間で最も寒かった」と言う人もいました。酷暑だった日本とは真逆だったんですね。 ただし、欧州系の人(白人)はTシャツ短パンだったりするので驚きます。ウーバーの黒人運転手さんとも、白人との体感温度のちがいについて話題になりました。 7年前のように、ジンバブエ人画家のチェンジェライさん夫妻にも再会できました。なんと来年、チェンジェライ画伯はジンバブエの国立美術館で個展を開催するとのこと。青空市で作品を手売りしてた時代の彼を知っているだけに、それを聞いて私も嬉しかったです。 ちなみにウーバー運転手さんもジンバブエ出身者がとても多かったです。また、女性の運転手さん(カメルーン育ちとのこと)にも一人だけですが遭遇しました。 極楽鳥花が咲き乱れてました。 背後には西洋のお城の形の「キャッスル・ロック」。 でもケープタウンの山といえば、「テーブル・マウンテン」ですね。 ときおり、雲の「テーブルクロス」がかかります。 ケープタウンは2回目ですが、ケーブルカーではじめてテーブル・マウンテン頂上にも行きました。南ア初の黒人大統領ネルソン・マンデラが18年間囚われていた監獄島(ロベン島)を確認。 喜望峰も21年ぶり2回目です。世界屈指の美しい景色を楽しめる車道「チャップマンズ・ピーク・ドライブ」からサイの形をした岩山を眺めました。インスタ映えするカラフルな家が並ぶボカープ地区(マレー系ムスリムが居住)を散歩。左奥にテーブル・マウンテンが見えてますね。ボルダーズビーチでは、これも21年ぶりにケープペンギンたちに会えましたが、個体数が激減しているからなのか、柵が設けられており、観光客は以前のように近づくことができませんでした。 今年7月の袋井イベントの帰りに訪れた「掛川花鳥園」のケープペンギンのほうがもっと間近で見ることができました(笑)。 😎ジャン=リュック・ゴダールごっこ@ケープタウン pic.twitter.com/ds9VmDYsc8 — 梅田洋品店 (@UmedaYoHinTen) October 7, 2023 ケープタウンでは御覧いただいたように旧交を温めたり、観光したりがメインでしたが(笑)、しっかり買付けに関する情報を入手しました。...
オニャンコポンについて
更新日:2024/1/31 下記は当店が(趣味でこっそり)運営するX(旧ツイッター)のアカウント「アフリカのことわざ」で人気の句です(名称がXになってから自動配信は止められてしまいましたが。復旧準備中です)。 「ニャンコポン神が定めた運命は避けられない」 ガーナ(アカン人) 「うつぶせ寝では、ニャンコポン神は見えない」 ガーナ(アカン人) 「ニャンコポン神が殺さないのに、凡夫が殺そうとしても、あなたは死なない」 ガーナ(アカン人) いずれもガーナのアカン民族のものです。「ニャンコ」が猫を連想させるのはもちろんですが、「アカン」が関西弁を思わせるのも人気の秘密かもしれません。 なお、X(旧ツイッター)では字数を減らすために「民族」ではなく「人」で統一してます(アカン人、マサイ人、ズールー人等。「族」は個人的になんとなく違和感があるので使ってません)。 * ちなみに、「ニャンコポン神」という表現は、山口昌男『アフリカの神話的世界』で使用されていたのを拝借しました。この本にはニャンコポン神についての様々な物語が載っています。 ニャンコポンは「オニャンコポン」「ニャメ」とも呼ばれ、字義通りには「偉大なる者」という意味だそうです。全知全能の天空神です。ただし、知り合いのガーナ人に聞いたところ、「人の心のなかにいる」とも。 * ニャンコポン神は、なぜ天空の神となったのか。Wikipedia日本語版の「オニャンコポン」の項にもほぼ同じ説明がありますが、ここではOxford Referenceに書いてあることを意訳します。 そもそもは、天空神オニャンコポンは人々のすぐ近くに住んでいました。しかし、神は空の頂きに引っ越すことを余儀なくされました。というのも、ある魔女がヤムイモを打ち砕くとき、杵を神にぶつけてしまったからです。 魔女は何が起こったのかを理解すると、すべての臼を集めて積み重ねるよう、子どもたちに指示しました。 子どもたちは、できる限りのことをしましたが、オニャンコポンに到達するためには臼があとひとつ必要でした。魔女は子どもたちに言いました。積み重なった臼のいちばん下からひとつ抜いて、それを使いなさい。子どもたちはそうしました。積み重なった臼はぐらつき、崩れ落ちました。転がる臼が多くの人を殺しました。 この事件以来、「偉大なる者」は人々から遠く離れたままです。しかし、近づきにくい者とは決して見なされていません。精霊アボソムたちにはそれぞれに司祭がいて人間との仲介をしますが、オニャンコポンに司祭はいないからです。 英語原文ではキリスト教の伝統からか、神の代名詞がheとなってましたが、オニャンコポンに性別は無いようです(ガーナ在住Sさん調べ)。 また、阿部年晴『アフリカ神話との対話』によれば、同じような話はガーナ以外の西アフリカ諸国にもあるようです。 なお、こちらが現在もガーナで日常的に使われている杵と臼(と魔女…ではないです!)。 * たまに聞かれるのが、「ニャンコポン」と「オニャンコポン」のちがいです。オニャンコポンの「オ」は日本語の敬語の接頭辞「御」を思わせます。「お礼」「お箸」などの。 でも、いつもガーナでお世話になっているSさんによれば、たんに「方言の違い」と考えればいいそうです。「マックとマクド」、「ヤマザキさんとヤマサキさん」のようなものでしょうか。 いずれにせよ、日本人にはオが付いた「オニャンコポン」のほうが好まれてるようですね。漫画『進撃の巨人』やゲーム『逆転裁判』の登場人物、アニメの作品名、競走馬の馬名にも使用されています。 負けたホープフルSを糧に会心の勝利!きのうの京成杯を鮮やかに差したオニャンコポン=菅原明良騎手。このガッツポーズでした。昨年、涙の東京新聞杯(カラテ)に続く重賞2勝目。デビューから31、30、75勝。4年目シーズンの今年は飛躍が期待できる若手です。#オニャンコポン #菅原明良 pic.twitter.com/DkZUO6s6Rr —...
作品紹介「セミオーダー/ポケット付きワイドパンツ」
こんにちは、梅田洋品店です。 今回ご紹介するのはセミオーダーの「ポケット付きワイドパンツ」です。 布柄はもちろんですが、幅(もも幅、裾幅)もS・M・Lの3サイズからお選びいただけます。 私、梅田がサンプル(型見本)を履き比べた写真です。 写真では特に裾幅を見ることでサイズの違いがわかるかと思います。 ウエストは ゴムと紐で調節できます。 丈は足首の長さにすることで、「脚長効果」やエレガントさを引き出せますね。後ほどご案内するように、お好みの長さに調整いたします。 まずは「Sサイズ」ご着用のお客さまスナップをご紹介します。 以下は「Mサイズ」です。SとLの中間の幅の長さです。 そして最後に「Lサイズ」です。最も幅が広いデザインです。 丈は変更できますので、ご注文の際にご希望の長さをお知らせくださいね。 ★足首丈にする場合の目安身長150cm 股下60cm~65cm身長155cm 股下65cm~69cm身長160cm 股下69cm~72cm 以上、梅田洋品店の「ポケット付きワイドパンツ」のご紹介でした。参考にしていただけたら幸いです。 アトリエはもちろん、オンラインショップでもオーダー可能ですので、ぜひご検討くださいね。